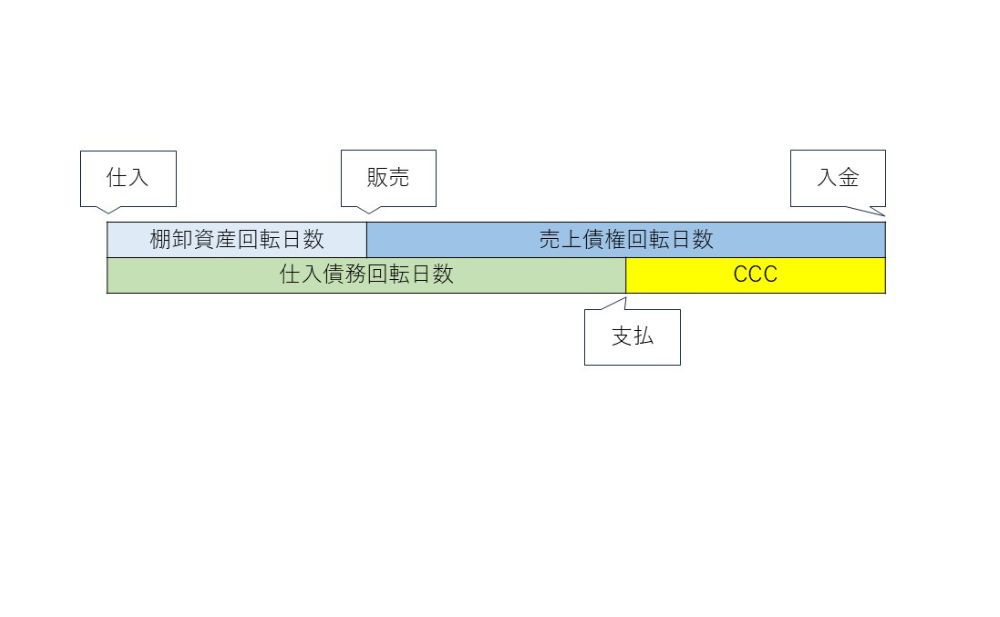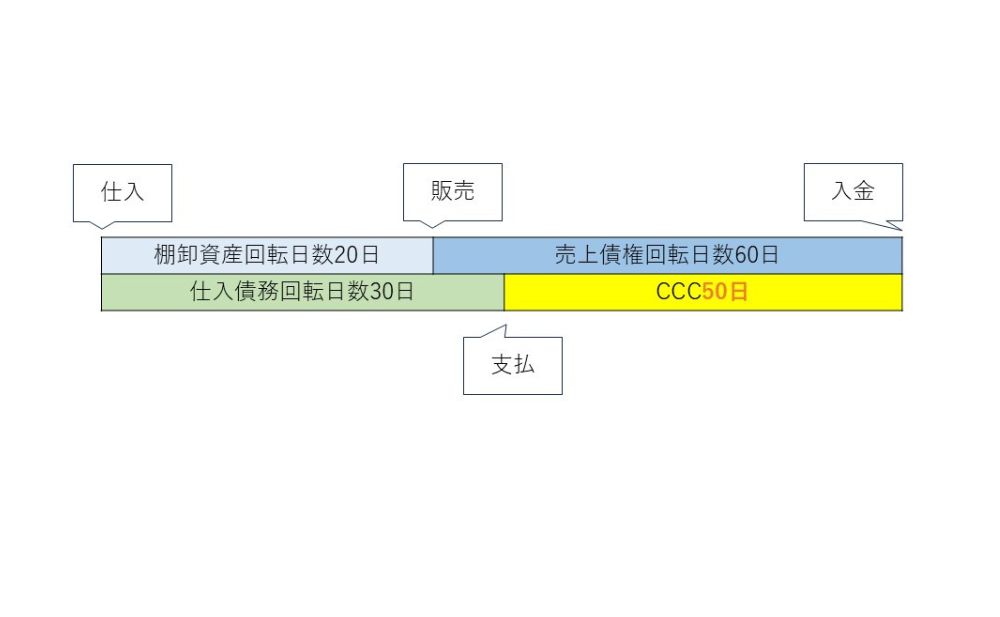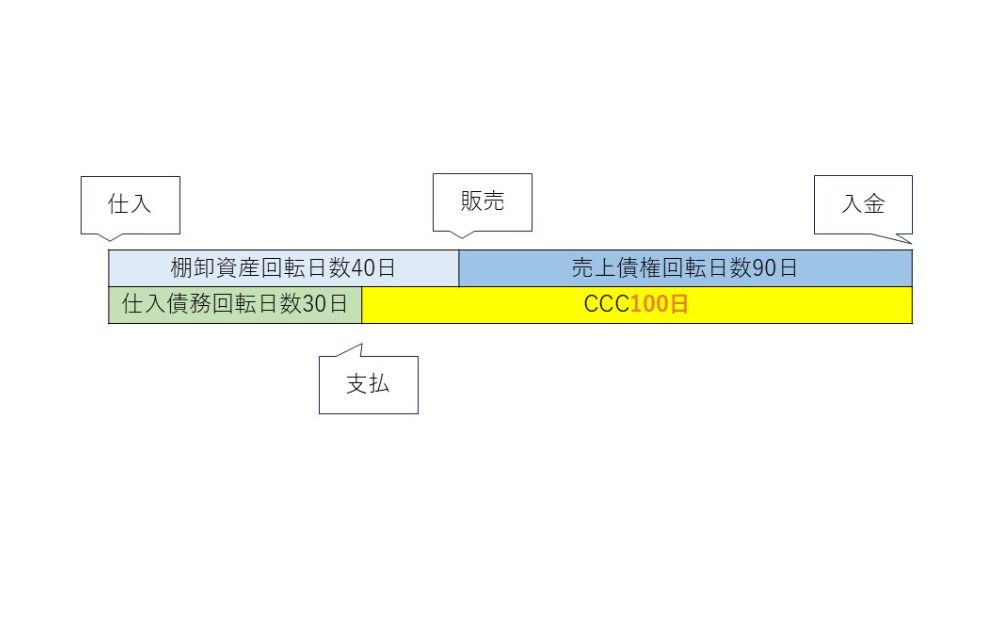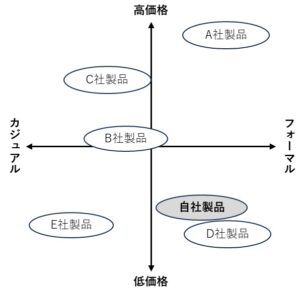赤字会社の共通項
皆さん、こんにちは。フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。
11月は出張も多く、非常に多忙でした。
大阪を拠点にしながら仙台、京都、岡山、山口、和歌山、福井、三重、東京と主に経営改善支援で各地を行脚してきました。
案件の多くはすでにリスケジュール(元本返済の減額または猶予)をしている、もしくはまもなくリスケジュールを行う支援先様で、財務状態が相当程度に毀損されています。
業種も規模も様々ですが、財務状態が著しく毀損されている会社の特徴は驚くほど似通っています。
私が経営改善の最前線で見てきた経営改善が必要な会社の共通項をいくつかご紹介しましょう。
1.過剰債務
慢性的な赤字に対して収益性の改善に取り組まず、金融機関から借りることで何とか資金を繋いできたパターンです。特にコロナ融資は満額借りた会社ほど、負債額だけが大幅に増加しています。融資が難しくなると次はリースバックやファクタリングなど限界まで資金調達に奔走し、どうにもこうにも行かなくなってから事の重大性に気づきます。
2.判断の遅さ
例えば新規開拓営業、値上げ交渉、経費の削減など、すぐに着手しなければならない事案であってもとにかく行動が遅いパターンです。様子を見る、今期はこのままで、業界の慣習だから・・・などの言い訳ばかりで行動に移すまでに数ヶ月もしくは数年を要するケースもあります。
3.行動量の少なさ
何か新しい取り組みを行う時、赤字体質の会社は1度行動を起こして結果が出なければすぐにやめてしまいます。例えばSNSやHPの更新などです。ビジネスの世界ではすぐに結果が出ないことが多く、継続性が要求されます。経費の削減など即効性のある取り組みも重要ですが、同時に中長期的な飯の種を蒔かなければなりません。しかし、赤字体質の会社には継続性が全くなく、諦めるのが早い傾向にあります。
4.外部環境に原因を求める
自社の弱みにフォーカスするのではなく、外部環境に自社の赤字の要因を求めてしまいます。自社の弱みに向き合わず、経営改善から逃げ、時間だけが経過してしまいます。
他にもありますが、上記4つの項目は経営状況の悪い会社の多くに共通する特徴です。
皆様も一つでも自社に当てはまる場合は、必ず考え方を改めてください。
中小企業を取り巻く環境は決して優しいものではありません。
経営に対して真摯に取り組む姿勢、結果やプロセスにこだわる姿勢は常に持ち続けましょう。