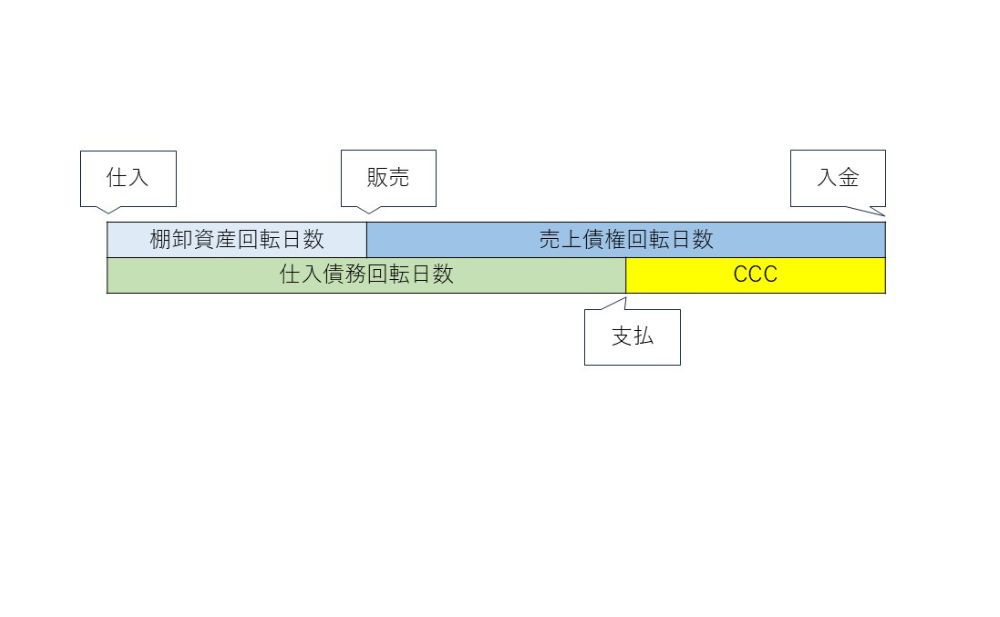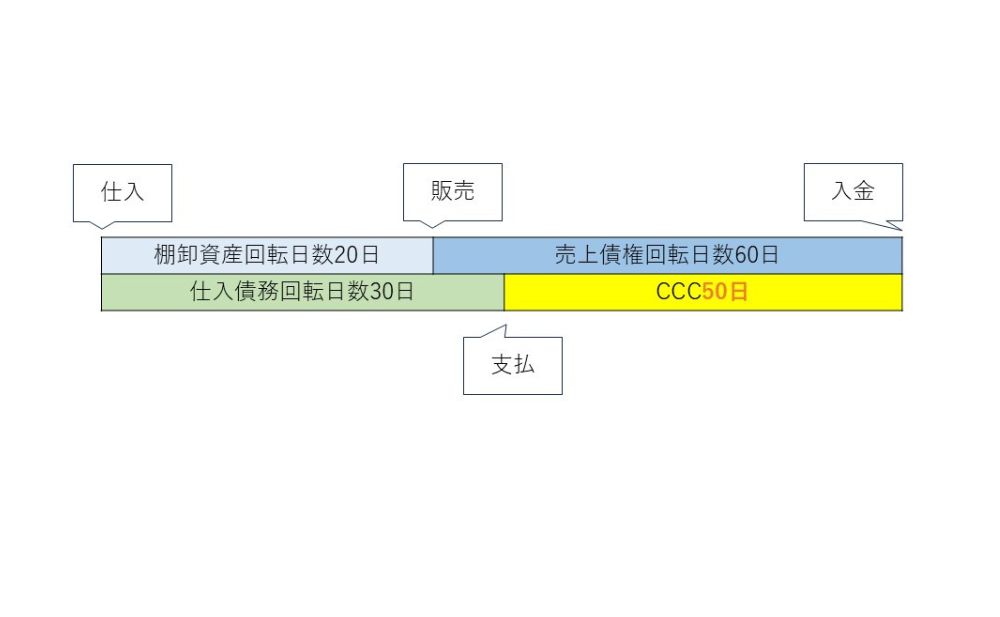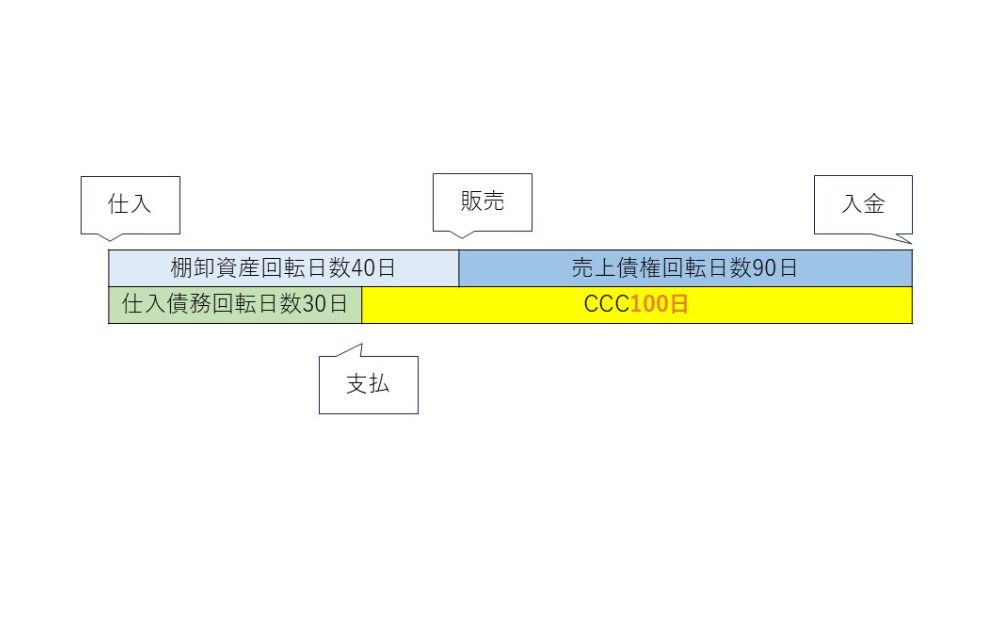会社を守れるのは経営者だけ
こんにちは。中小企業診断士の社内です。
今回はご支援に携わっている事業者様から私が学んだことを共有したいと思います。
資金繰りに困窮している事業者様で、金融機関様に今月から元本返済のリスケジュールを依頼しなければならなくなりました。
経営者様から一度金融機関様に依頼したところ、
「新規融資を出したばかりなので、せめてあと3か月は返してほしい」と断られてしまいました。
こちらの企業の毎月の元本返済額は160万円です。
残りの現預金が600万円を切っているのに、3か月も支払ってしまっては会社が潰れてしまいます。
このような危機に、経営者様から出た言葉は「とても言えそうにない。個人資産を使ってでも3か月分返済したい」でした。
元本返済のリスケジュールを行うと毎月の返済負担が軽くなりますが、原則新規融資は受けられなくなります。
個人資産の出番がないことが望ましいですが…
経営状態も芳しくない状態なので、今後のいざというときのために個人資産は取っておくべき手段ではないでしょうか。
今後本当に苦しくなった時に社員様を守るための資金です。
社員様の協力を得て経営を改善していくことはできますが、意思決定は経営者にしかできません。
会社の行く末を決めるのは経営者しかいないのです。
また、会社が立ち行かなくなってしまっては金融機関様にとっても貸し倒れになり困ります。
経営者様に考え直していただきました。
その後、経営者様が金融機関様の元へ赴いて直接お話をされ、今月からのリスケジュールを了承していただくことができました。
事情は様々あると思いますので一概には言えませんが、経営者の強い意志で状況は変えられるかもしれません。
様々な事業者様からお話を伺っていると、会社を立て直すのはまさに背水の陣だと感じます。
どんなに良い施策があっても、経営者様の強い意志がなければ成し遂げられないでしょう。
中小企業診断士 社内 愛里